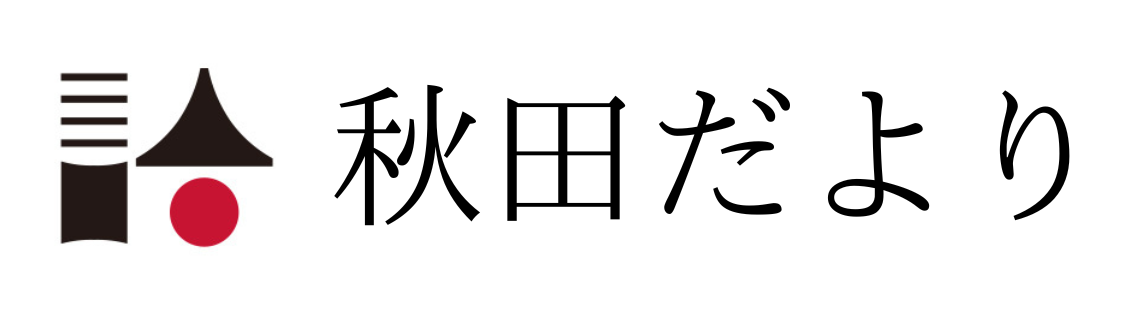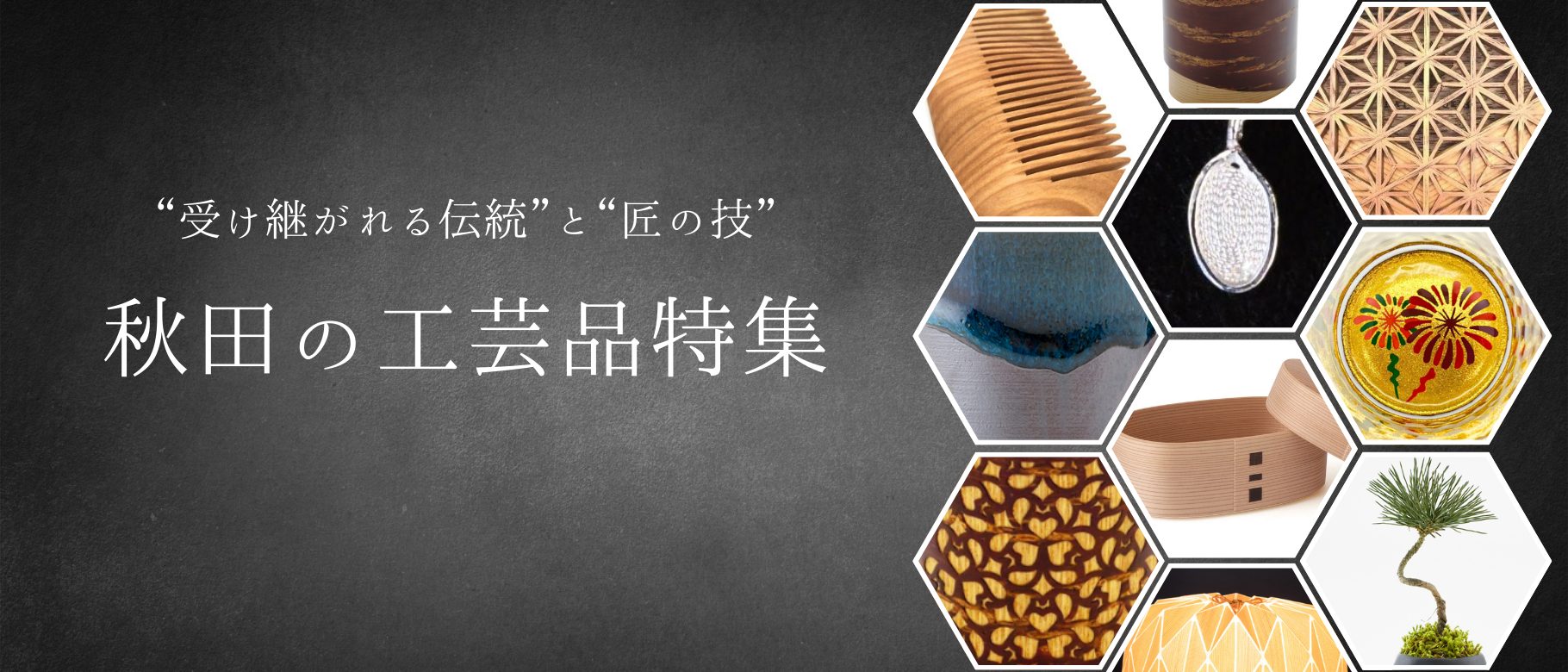木の香りと手仕事の温もりが詰まった曲げわっぱ弁当箱は、ご飯をふっくら保ち、毎日のお昼時間をちょっと特別にしてくれます。けれど「どのサイズを選べばいい?白木とウレタン塗装の違いは?」など迷う点も多いもの。
本記事では曲げわっぱの魅力や選び方、さらに2025年最新のおすすめ商品まで、初心者でもすぐに実践できる情報をまとめました。木の弁当箱が初めての方も、長年愛用している方も、読めばきっと曲げわっぱの奥深さを再発見できるはずです。
曲げわっぱとは?

曲げわっぱは日本の伝統工芸品
曲げわっぱは、スギやヒノキなどの天然木を薄く削り、熱を加えてやわらかくしたものを曲げて形作り、山桜の皮などで留めて完成させる日本の伝統工芸品です。お弁当箱として有名ですが、食器やひしゃく、おひつなどにも用いられます。天然素材ならではの優しい香りや、ぬくもりを感じられるのが魅力で、見た目の美しさと実用性を兼ね備えた道具として、今も多くの人に愛されています。
平安時代から続く伝統
曲げわっぱのルーツは非常に古く、平安時代の遺跡からも発見されています。日本各地で独自に発展し、それぞれの土地の自然や暮らしに合った形で受け継がれてきました。特に秋田県や福岡県などでは、伝統的工芸品として認められています。単なる道具ではなく、地域の文化や歴史を映し出す存在として、長く人々の暮らしに寄り添い続けているのが曲げわっぱの大きな魅力です。
秋田県・大館曲げわっぱ
秋田県大館市で作られる大館曲げわっぱは、曲げわっぱの中でも特に有名な存在です。樹齢200〜300年の天然秋田杉を使い、美しい柾目と明るい木肌が特徴。江戸時代、藩の内職として奨励され、400年以上にわたり技術が受け継がれてきました。1980年には国の伝統的工芸品にも指定。国内外で高く評価されており、大館曲げわっぱはまさに秋田県が誇る工芸品といえます。
曲げわっぱを使うメリット

冷めてもふっくら美味しいごはんを味わえる
曲げわっぱ最大の魅力は、ごはんが時間が経っても美味しいこと。天然木が呼吸することで、内部の湿度を自動で調整してくれます。炊きたてのごはんを朝に詰めても、昼にはふっくら柔らかいまま。特に白木や漆塗りの曲げわっぱはこの調湿効果が高く、プラスチック容器とは比べ物にならないほどの違いを感じます。
抗菌効果で夏場のお弁当も安心
杉やヒノキなど、曲げわっぱに使われる天然木には抗菌作用があります。そのため、特に気になる夏場でも、ごはんやおかずが傷みにくいという安心感があります。自然由来の抗菌性なので、添加物を使わずに衛生面を保てるのも嬉しいポイント。もちろん絶対ではないため、粗熱を取ってから詰める、冷暗所で保存するなど基本的な注意は必要ですが、曲げわっぱは一年中頼れるお弁当箱です。
シンプルな美しさでおかずが映える
曲げわっぱの優しい木目と、丸みを帯びたフォルムは、おかずをより美味しそうに引き立ててくれます。シンプルなごはんとおかずでも、曲げわっぱに詰めるだけで料亭のような上品さを演出。深さがあるため、おかずが立体的に見え、彩りも豊かになります。白木ならナチュラルな木目を、漆塗りなら艶やかで落ち着いた色合いを楽しめるので、好みに合わせて選ぶ楽しさも広がります。
軽くて持ち運びがラク
曲げわっぱは、見た目の重厚感に反して、とても軽いのが特徴です。天然木を薄く削って曲げて作られているため、手に取ると驚くほどの軽さを感じます。バッグに入れても重さが気にならず、通勤や通学、お出かけにもぴったり。さらに、角がない丸みのある形状なので、持ち運び中もかばんの中で収まりがよく、傷みにくいのも嬉しいポイントです。日々使うものだからこそ、この軽さは大きなメリットになります。
長く使うほどに味わいが深まる
曲げわっぱは、適切にお手入れをしながら使い続けることで、木の繊維が締まり、しなやかさと強さを増していきます。さらに、手の油や日々の使用によって少しずつツヤが出て、世界に一つだけの自分だけの風合いに育っていくのも魅力。壊れてしまった場合も、工房によっては修理対応してくれるところもあり、一生モノとして付き合うことも可能です。
失敗しない曲げわっぱの選び方

詩の国商店 オンラインストアより画像を引用
曲げわっぱのお弁当箱を選ぶときに、必ずチェックしたいのは「形・デザイン」「素材(塗装)」「サイズ(容量)」の3つです。見た目の好みだけで選んでしまうと、使い勝手に不満が出ることも。使うシーンやライフスタイルに合わせて、それぞれのポイントをしっかり押さえて選ぶと、長く愛用できるお気に入りの一品に出会えます。
形・デザインで選ぶ
曲げわっぱ弁当箱には、小判型、丸型、そら豆型(はんごう型)、スリム型など、さまざまな形があります。スタンダードな小判型は詰めやすく、どんなおかずにも対応できる万能タイプ。丸型は丼ものや三色弁当がきれいに映え、そら豆型は個性的で可愛らしい印象に。スリム型は持ち運びやすく、バッグにもすっきり収まります。自分の食べたいお弁当スタイルや持ち歩きやすさをイメージして選びましょう。
素材(塗装)で選ぶ
曲げわっぱの素材には、白木(無塗装)、漆塗り、ウレタン塗装の3タイプがあります。お手入れ重視なら、洗剤が使える漆塗りやウレタン塗装が安心。天然木の香りや調湿性を最大限楽しみたいなら、白木がおすすめです。ただし白木はお手入れに少しコツが必要なので、最初はウレタン塗装で慣れてから本格的な白木にステップアップするのも一つの方法。ライフスタイルや使い方に合わせて素材を選びましょう。
サイズ(容量)で選ぶ
お弁当箱は、食べる人に合わせた容量選びが大切です。一般的に「ml数=カロリー数」と考えられており、400~500mlなら少食~普通量、600ml以上ならしっかり満腹感を得られる目安になります。二段式のお弁当箱なら、ごはんとおかずをたっぷり詰め分けることも可能。お子さん、女性、男性と、それぞれの食べる量やシーンに合ったサイズを選ぶと失敗がありません。
曲げわっぱ弁当箱おすすめ5選
大館工芸社 小判弁当

大館工芸社より画像を引用
大館工芸社の小判弁当は、日本三大美林・秋田杉の美しい木目を活かした伝統工芸品です。明るく優雅な風合いと、軽さ、弾力性を兼ね備え、日常使いにぴったり。ウレタン塗装が施されているため、唐揚げやチャーハンなど油分の多い料理も安心して詰められ、使用後は食器用洗剤で手軽に洗えます。木の温もりを感じながら、毎日のランチタイムがちょっと豊かになる一品です。
| 料金 | 9,350円 |
|---|---|
| サイズ | 180×110×50mm |
| 容量 | 490cc |
| 公式HP | https://magewappa.co.jp/products/16 |
柴田慶信商店 小判弁当箱(中サイズ)

柴田慶信商店より画像を引用
秋田県大館市の伝統工芸品である曲げわっぱ。天然秋田杉を使用し、無塗装で仕上げられているため、木の香りや調湿効果を最大限に楽しめます。仕切り付きで使いやすく、軽量で持ち運びにも便利。使い込むほどに味わいが増し、長く愛用できる逸品です。
| 料金 | 12,100円 |
|---|---|
| サイズ | 160×102×55mm |
| 容量 | 約580〜600ml |
| 公式HP | https://magewappa.com/products/koban |
栗久 弁当箱・小判型(スリム)

栗久より画像を引用
樹齢200〜300年の秋田杉を使用し、職人の手で丁寧に作られた高級感あふれる一品。無塗装で木の風合いを楽しめ、ご飯がくっつきにくく手入れもしやすい。スリムな形状で持ち運びにも便利です。
| 料金 | 15,400円 |
|---|---|
| サイズ | 200×110×57mm |
| 容量 | 600cc |
| 公式HP | https://www.kurikyu.jp/shop/bento/koban-slim.html |
りょうび庵 あすか弁当箱

りょうび庵より画像を引用
伝統と現代の使いやすさを融合させた、りょうび庵のあすか弁当箱。秋田杉の美しい木目を活かしながら、ウレタン塗装で油物にも対応。食器用洗剤で洗えるので、お手入れも簡単です。
容量は600mlと普段使いにちょうどよく、軽量で持ち運びにも便利。毎日のお弁当時間がちょっと贅沢になる、こだわりの逸品です。
| 料金 | 11,000円 |
|---|---|
| サイズ | 160×125×60mm |
| 容量 | 600ml |
| 公式HP | https://www.ryobian.jp/products/RB-360/ |
曲げわっぱ工房 E08 KOBAN(被せ)松 約450ml

曲げわっぱ工房 E08より画像を引用
樹齢150年以上の天然杉を使用した無塗装(白木)の小判型弁当箱です。ごはんの余分な水分を調整し、ふっくらとした美味しさをキープ。夏場でも傷みにくいのが嬉しいポイントです。自然素材ならではの呼吸や経年変化も魅力のひとつで、使い込むほどに風合いが増します。丁寧に乾かすことで長く愛用できますよ。
| 料金 | 14,300円 |
|---|---|
| サイズ | 本体:約104×149×35mm 蓋込み:約123×160×35mm |
| 容量 | 約450ml |
| 公式HP | https://e08.jp/collections/lunchbox/products/koban-k-sho |
まとめ
曲げわっぱ弁当箱は、木の香りと職人の技が詰まった、日本ならではの伝統工芸品です。今回ご紹介した5選は、初心者でも扱いやすいものを揃えました。形やサイズ、素材によって使い心地はさまざま。自分のライフスタイルや好みに合わせて選べば、毎日のお昼時間がもっと特別なものになるはずです。ぜひ、お気に入りの一品を見つけてくださいね。